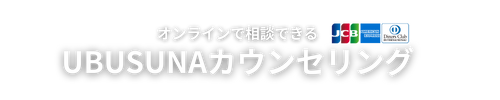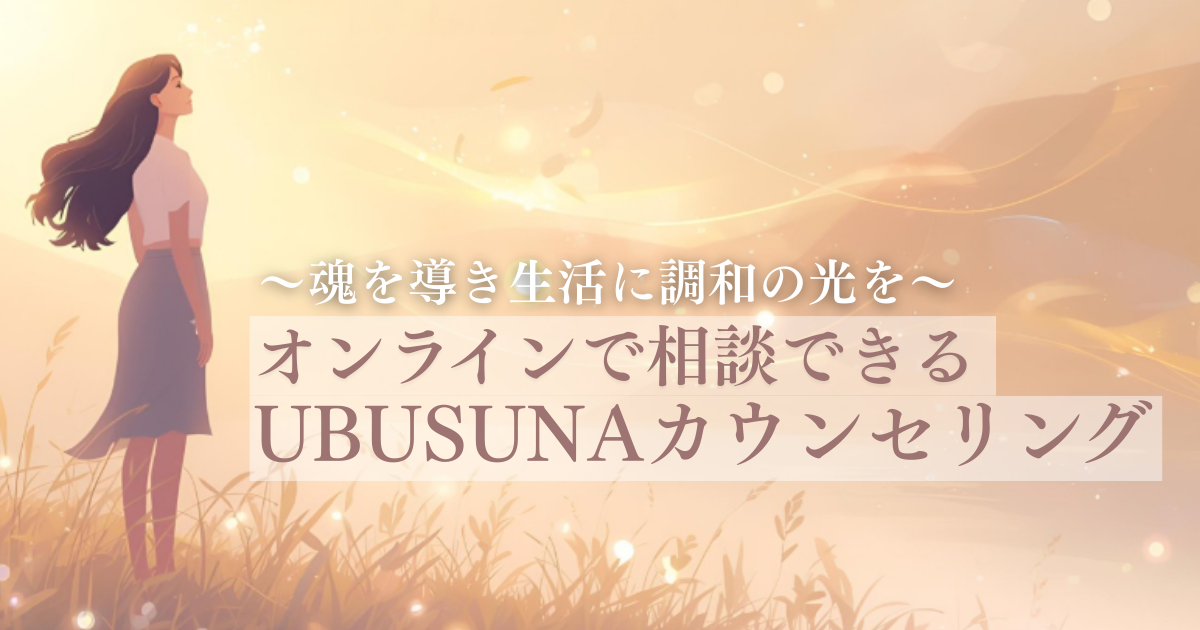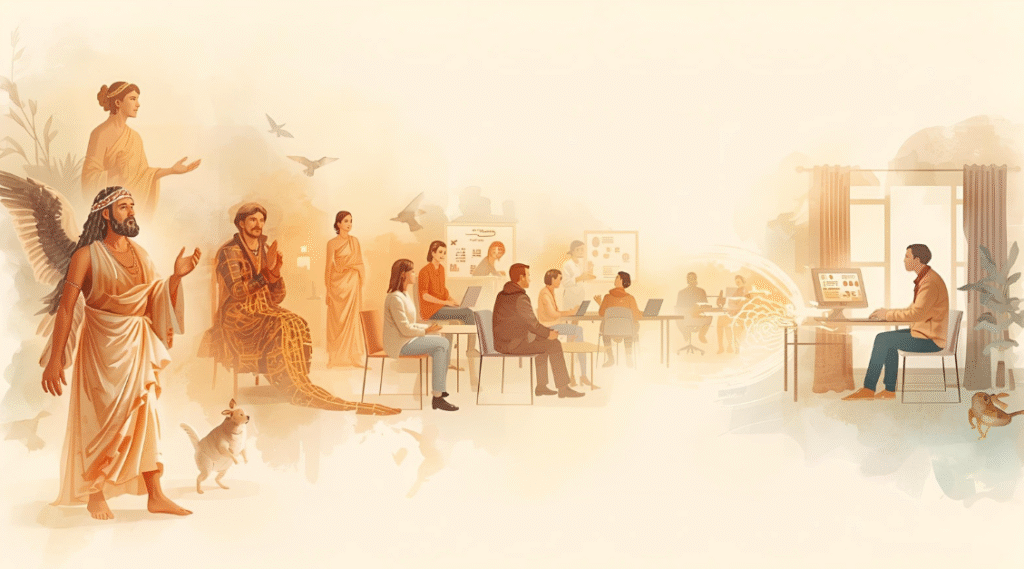
カウンセリングの始まりはとても古く、宗教的な儀式やシャーマンの祈り、牧師への告解など、人が心を打ち明ける場面にその原型を見ることができます。
近代に入ると、1900年代初頭のアメリカで「職業指導運動」「精神測定運動」「精神衛生運動」といった社会的な動きが生まれ、適性検査や心理テスト、心の健康という観点からカウンセリングが体系化されていきました。
さらに第二次世界大戦後には、退役軍人の心のケアが必要となり、心理学を土台にしたカウンセリングが大きく発展していきます。
1940年代にはカール・ロジャーズが「来談者中心療法」を提唱。専門家が答えを与えるのではなく、相談者自身が自分の中から答えを見つけていくことを重視したこの考え方は、従来の医師主導型から大きな転換をもたらしました。ロジャーズの理論は、カウンセリングの方法や目的、そして倫理観にも深く影響を与えています。
日本では戦後にカウンセリングが導入され、1950年代から学校や企業で広がっていきました。その後、1988年には臨床心理士が、2015年には公認心理師が国家資格として誕生し、専門家としての地位が確立されます。
現在のカウンセリングは、認知行動療法をはじめとするさまざまな心理療法が取り入れられ、時代のニーズに合わせて進化し続けています。日本独自の発展も見られ、教育、職場、家庭など幅広い場面で「心の支え」として重要な役割を担っています。